横光利一の葬儀の日=1948年(昭23年)1月3日、早大仏文科在学当初より横光に師事していた八木義徳は運び出される棺を、先輩の人とともにかついだ。それを目撃していたのが、生涯横光利一を研究の対象としつづけ、先ごろ死去した保昌正夫であった。
八木は在学中より仏文科を創設した吉江喬松の識見、人物に敬愛の念を抱いてはいたが、文学上の師としては横光一筋であった。『旅愁』を書き、戦時下はミソギにも加わった横光。戦後はそういう横光に対してきびしい批判の矢が放たれたが、八木はいついかなるときとて、横光師事、横光の門下生という意識を頑固に持ちつづけた。八木の作風そのものは、横光のめざした昭和文学の開拓者というようなかたちではなかったのだが、ひとたび門下として名を連ねた以上、それをかたくなに守り切るのが八木義徳という作家の生きかたであり、八木の流儀であった。このことは保昌も十分意識し、石塚友二と八木義徳を横門の代表的存在として書いてもいる。八木たちがはじめた同人雑誌「黙示」(きわめて入手困難)については、いずれ別のかたちで述べたく思っているが、ここでは彼の出世作=芥川賞受賞作「劉広幅」について判明した事項をも含めて眺めていきたい。
普通「劉広福」は戦時下の末期に統合された「日本文学者」(昭和19年4月1日)創刊号が初出、ということになっている。たしかに「日本文学者」掲載の「劉広福」によって芥川賞受賞となったのだが、その前段階の初稿ともいうべき「劉広福」があったのである。しかもそれは「満洲観光」と称する「連盟報」に掲載されていた。「康徳8年6月1日」発行の第5巻第6号である。日本政府の規定による満洲国の建国が1932年、34年が「康徳元年」である故、「康徳8年」は「昭和16年」にあたる。「満洲観光」は「満洲観光聊盟」(奉天春日町鉄道総局内)を発行所とし、発行人は野間口英喜(奉天市雪見町4-3-7)、編集人は佐藤真美(奉天朝日街四段9-2-22)。奉天の町の地名まで日本流にしてしまっているのにも驚かされる。満洲観光連盟規約の第二条には、
「本連盟へ観光委員会ノ指導二基キ在満観光事業関係機関相互ノ連絡協調ヲ回リ観光事業ノ統制発達ノ期スルヲ以テ目的トス」とある。
会報ではあるが、その目次を一瞥すればわかるように、満洲の風土、特質を知らしめる啓蒙的記事、観光に関する事項とともに、満洲への誘いとしての詩、俳句、エッセイの類、それに小説が掲載されている。
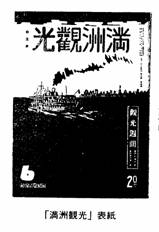
表紙 樋口成章・カット 佐藤功・松村松次郎
国民厚生運動と観光 藤森章
観光週間への期待 花本嗣郎
初夏随筆 アカシア並木 紫藤貞一郎
朝三態 加納三郎
或るドイツ人の旅の印象(翻訳) カー・ハー・アイケルト 植村敏夫訳
六月のカメラ 新緑とハイキング 伊達良雄
松花江(詩) 坂井艶司
満洲歳時記 金丸精哉
グラフ 満洲の河
特報・満洲の河川
地質学上から見た満洲の河川 斎藤林次
遼河と文化 田口稔
満洲の川点 西尾新六
臨江雑記 千田万三
北満の河運 中原実
松花江を下る 日向伸夫
松花江(俳句) 望月龍
旅への誘ひ 山田健二
劉広福(小説)八木義徳
観光通読 観光週間
週刊誌なみの大判、全38ページ。右の誌上で知られている文学者といえば、日向伸夫と八木義徳の二人のみといってもよく、あくまでも啓蒙性の強い満洲観光の会報であり、文芸的色彩はまったくそえ物といってよい。広告を見ても、日本海汽船の「一番近い日満連絡」と題し、その月の新潟行、敦賀行の汽船の日程が明記されている。満洲への誘いはなされていても、五族協和、王道楽土のスローガン的要素はきわめて少ない。
八木は1937年(昭12)2月号の「早稲田文学」に「海豹」を発表し、横光にはじめて賞められた。しかしその年の6月に父が死去。翌年の3月、大学を卒業し、亀戸のミヨシ化学工業に入社したが、8月に満洲国奉天市鉄西工業地区に新会社(満洲理化学工業)を設立するため渡満。「以後四年間文学から全く遠ざかる」と「年譜」に記されているが、これはいささか強調したいいかたとなっている。実は渡満の翌年のこの「満洲観光」に「劉広福」の初稿をそっと発表していたのである。この種のものは他にはないと思われるので、「文学から全く遠ざかる」とも言ってもやむを得ないことでもあった。しかし私はこの「観光案内」の初稿「劉広福」を読み、それが「日本文学者」掲載の「劉広福」と較べてみたくなった。基本的には変らないのだが、「満洲観光」誌上の「劉広福」には、ひとつの重要なエピソードが欠落していて、全体としてそれがためふくらみがなくなっている。削りとる初稿もあるが、つけ加えることで
効果がさらに増す初稿もある。
志賀直哉の「白樺」創刊号に掲げた「網走まで」にも初稿があり、久しく放擲されたままであったが、没後の岩波版の全集において、最初に構想されていたものをも添えた。それで明確になったことは、志賀のテーマの散漫を削りとるための徹底した削除、推敲。それは「剃刀」(初稿が三種もある)においても、また「大津順吉」においても、そのようなことが見られた。
八木の場合、「満洲観光」という小説はそえもののような小冊子であり、ページ数もそれほど多く与えられていなかったのであろう。初稿の「劉広福」― 工場の職工の一人ではあるが、構内の「屑拾ひ、水はけ、風呂焚き、石炭の濾し篩ひ、他の職工たちの汚れものの洗濯、炊事、走り使ひ、謂はゞ雑工の中の雑工 ―であり、「ひどい吃り」と「巨大な体躯に不釣合な動物じみた童顔」の満人であった。
八木は結婚した妻をも連れての満洲行きであったが、1943年(昭和18)、満洲理化学工業を退社して東京に帰り、長男も生れ、東亜交通分社に入社もするが、翌44年(昭和19)2月、「劉広福」を「脱稿」、3月に応召、というまことに当時の日本人の一人として、今から思えば実直で、大変な目に逢う。応召逃れを要領よく果し、それが反戦的だと自慢げに書いている人たちとは異なっていたのである。この応召前の「脱稿」という作業が、実は「満洲観光」誌上のものの推敲をさすと私は見る。ひとつのエピソードを大胆に挿入することがもっとも大きな推敲であるのだが、よく較べあわせてみると随所に小さな、しかし作品を豊かにする具体的な推敲が実は行われていたのである。「満洲観光」の「劉広福」の冒頭は、劉広福を職工として雇ひ入れるについては、はじめから難色があった。職工といっても、私の工場では、それは雑工ともいふべきもので、ほとんど技術など必要とせぬものであったし、ちょうどその時は古い職工たちが盗みをはたらいてかなり人数が馘首されたところであったので工場としてはほんとに猫の手でも欲しいところであった。工場の作業が機密を要する性質のものなので、いつも職工は雇ひ入れについては少なからず難しい条件を出す工場長もこの時ばかりは何の註文もつけず一切を私に委せるといふことになった。工人招募といふ貼紙を見て、事務所の玄関は大勢集って来た応募者の中から、私は老人と子供は先づ問題外として除き、他は姓名と年齢と学
歴とを質ねるだけでほとんど詳細な身許など調べずにみな採用することにした。
「日本文学者」の「劉広福」では、
劉広福を工人として雇ひ入れるについては、最初から難色があった。当時私の勤めてゐる工場では、第一期の増産計画に対応する増築工場が一棟新らしく完成したばかりのところで、これにかなり多数の工人を必要とする時であった。
現在ではもちろんそんなことはないが、当時の満洲はまだ労働力の潤沢な頃で、その募集の方法も極めて呑気且つ簡単なものだった。事務所の玄関前か工場の煉瓦塀に「工人招募」といふ貼紙を二三枚もペタペタ貼って置けば、結構応募者が門前に市をなすといふ時であった。で、その時も募集の方法はこれに従った。驚いたことには、その「工人招募」といふ三四枚の貼紙を工場の煉瓦塀に貼り終るか終らぬうちに、既に事務所の玄関には応募者の群が犇めき合ってゐた。その奉天の工場地帯には、満洲の奥地や北支の山東辺りから職をもとめて大量に流れ込んで来た貧農や下級労働者や苦力たちの群が、三人四人時には十人二十人と大きな隊を組んで絶えず工場街を遊弋【ゆうよく】して歩き、「工人招募」といふ貼紙を見つけた途端にドッとそこへ雪崩込むといふ寸法であった。応募者の中には、つい筋向ひの工場のマークのついた制帽を平気で頭に載つけたのも四五人混じつてゐた。これは、すこしでも楽な、そしてすこ
しでも賃銭の高さうな工場を狙って、転々と節度もなく飛び移って行く最も悪質な手合であった。
工場の作業が機密を要するものなので、いつもは工人の雇ひ入れについて少なからず難しい条件を出す工場長も、なにぶん増産々々の懸声に追はれてゐた時なのでこの時ばかりは何の註文もつけず一切私に委せるといふことになってゐた。私自身はべつに労務係といふハッキリした職名を持ってゐるのではなく、事務所の庶務をやる傍ら工場の方の人事の面倒もみるといった、職制の極めて呑気な工場であったが、しかし工員を全部合せても僅か五十名足らずといふ小さな工場のことで、これまで別にたいした不都合もなくやってこれたのであった。(もっともその後、正式に労務係といふものは出来たことは出来たが)
私は事務所の玄関に大勢集って来た応募者の中から、老人と子供は先づ問題外として除き、他は姓名と年齢と学歴と前歴とを質ねるだけでほとんど詳細な身許など調べずに採用することにした。
小説の冒頭の部分のみを比べると、骨子は変らないが、「日本文学者」のほうがその場の状況がいかにこまやかに書き加えられていることか。ふくらませることによって、異常な場における状況と雰囲気がいかに増殖するか、まざまざとわかってくる。そういうなかで、どうしても納得せずに帰らなかった男、それが「劉広福」であった。
ひとつの大きなエピソードというのは、「或る事件が」と書かれてある前に、一生懸命お金を貯めたいという「劉広福」に、実は「若い満人の女性」(許婚者)がいたという事実がくわしく書き込まれている部分である。「吃り」で、童顔の「大男」で、仕事はテキパキ骨惜みせず働く劉広福。「嫁はみな謂はゞ金で買ふ」というのが彼らの風習であった。女性は日本人の経営する「スミダ町、よねや」で下働きをしているという。
「劉広福」とその女性。盗みの問題で疑いが晴れたとき、男は「獣の咆哮」を放ち、女性もそこに走り、声をあげて泣く。二人は「大木にとまった蝉」のようであり、「その哭き声の二重奏」によって、書き手の「私」の心も大きくゆるむ。その背景に劉らの「錦州?」と反対の「関東洲」との交争も実はあったのである。
「劉広福は晴天白日の児となつて工場に帰って来た。事務所の連中が口々に『劉!多々辛苦!』と言って迎へると彼は流石にニコニコして相好を崩しながら、しかし『没法子』とたゞ一言答へるきりであった」という部分も「満洲観光」のほうには書かれていなかった。盗みは減るし、工人らの自治制も劉の存在によって形を整えてくる。会社側も一石二鳥。それに「或る事件」― 新参の職工の不注意によって生じた火災 ―が生じたが、「劉広福」が水の滴が落ちるボタ布の束を抱え、迅速な行動で爆発をくいとめる。そのため彼は顔面と両手に大火傷をする。この時も「獣の咆哮に似た一声」を彼はあげて飛び込んで行った。病院でも彼は苦痛に耐え切った。二週間で癒って退院。そこに動物のみずからの力で傷をなおす才能をあらためて感ずる。天涯孤独の彼ではあったが、あの女性がいた。「満洲観光」のほうでは、前のエピソードを省いているため、あの女性は、最後まで出て来ない。彼の冒険的行動は仲間の敬意
を集める。その末尾もつぶさに見ると、
劉広福は今でも私の工場に(初稿では「で」)働いてゐる。 最近彼は那娜と晴の結婚式を挙げた。(この一文は初稿てばなし)彼の名は現在、私の工人名簿の中では第一位を占めてゐる。(初稿では「そして彼の名は現在私の職工名簿の中では第一位を占めてゐる」)
この「「劉広福」が芥川賞を得たときの「文藝春秋」と「日本文学者」との目次を較べてみたい。「日本文学者」では、
声明書 日本青年文学会
戦ふ日本文学の栄光 対馬正
性格と決意 渋川驍
革新の現実と形象の発展 牧野学
白老部落(随筆) 佐々木純雄
芸術家の放れ業(随筆) 岡本謙次郎
はじめの時(詩) 阿部寅之介
遺書(詩) 正木哲夫
雪(詩) 菅藤則男
手(詩) 柴田忠夫
「試み」の問題(文藝時評) 高山毅
小説の隘路(文芸時評) 田宮虎彦
文学の郷愁について(評論) 矢崎弾
われらは竝く戦ふ 今井潤ら
劉広福(小説) 八木義徳
嫁の日記(小説) 吉川江子
出陣の賦(小説) 山村良次
梅白し(小説) 浜野健三郎
編集後記

表紙の「不易炎」は棟方志功。芥川賞候補となった八木の「劉広福」と浜野健三郎の「梅白し」が同じ誌面に並んでいたのである。この戦時下の末に合同させられた同人誌「日木文学者」である故、時局への配慮はそれなりにうかがえる。広告にしても、「決死の報道班員が 遂に敵沈撮影に船 沈撮影に成功した!!」という宣伝文句で、映画「轟沈」が大きく掲げられていた。「文藝春秋」(昭和19年4月)のほうは、
元老院のこと(随筆) 桑木厳翼
書斎雑記(随筆) 山口青邨
晩年の広重(随筆) 高橋誠一郎
南瓜煩(随筆) 井手成三
伝統(随筆) 鏑木清方
地方文学の曙光 岸田国士
北地を耕す人々 吉田十四雄
戦国武士の心構へ 高柳光寿
晴天に想ふ(詩) 神保光太郎
佃田(小説) 中山義秀
旅愁(第五篇第二回) 横光利一
劉広福(芥川賞受賞作) 八木義徳
真心記(随想) 菊地寛
聖戦歌抄
聖戦句抄
窯の火(入選短歌) 鎌田貞雄
方向舵
編集後記
表紙は伊原宇三郎、目次絵は鈴木信太郎この時代は今とは異なり、選評は前月の9月号にすでに掲げられていた。「劉広福」と小尾十三の「登攀」が同時受賞。候補作に林柾木の「昔の人」猪股勝人の「父道」、浜野健三郎の「梅白し」、妻木新平の「名医録」、劉寒吉の「古戦場」、若杉慧の「青色青光」、清水基吉の「雨絃記」、儀府成一の「碑文」などがあげられていた。
八木を強く押したのは横光である。「不用な枝葉を惜しげもなく切断し、鮮明に幹の太さを浮き上らせたカットの手腕は、主材の底まで眼力の届いてゐることを証明してゐる。クライストの短篇に似た、一見、乱暴粗雑かと見えるこの手法を選んだ裏の繊細さ、大胆さの、見事に定着した強さが、熱しほとばしり、読者の面を撃って来る。数年前、一度この作者は、尾崎一雄氏の『陽気眼鏡』授賞のさい、草原地帯の美しい描写で首位を競ったことがあったが、この度の授賞の幸運は当然だらう」と称賛している。佐藤春夫も「あの素材を越してそれを生かすために太い線でぐんぐんと小細工なくひた押しに叙述する工夫で、しょう稍通俗に月並になりやすい話柄を品格賎しくなく仕立て上げ主人公の性格を生かしたのは手柄であらう」と称賛。川端も二作採るべしとの意見、河上徹太郎は「登攀」を強く押し、「劉広福」は他の審査員が述べるであろうとやや消極的、瀧井孝作は林柾木の「昔の人」の、ガサツな対局に向
かない小説を推していた。「満洲観光」の初稿をカツチリと書き改めた故に、主人公が鮮明なかたちで浮びあがったに違いない。それを収めた創作集については次回に述べたい。八木の父の出身地は実は山梨県。医師であったので室蘭に移ったため、室蘭との縁が深いが、はじめの妻と子が、応召、捕虜生活中に戦災で死去。その後八木はながらく独身、ついで結婚したのが山梨県出身の正子夫人。小尾十三も山梨県出身、その二人の受賞は山梨県にとってはきわめて稀有なケース。ただし晩年におけるこの二人の文学者の差異はきわめて甚大。八木は耐えて、書ききり、美しいみごとな成熟を示す全集を残した。
〔こうの・としろう早稲田大学名誉教授〕
― 国文学解釈と鑑賞 平成17年12月号 より転載