八木義徳の芥川賞受賞作の「劉広福」は、彼の第一創作集『母子鎮魂』の末尾に収められている。『母子鎮魂』は「昭和23年3月5日」発行、土田喜三を発行者とする世界社(文京区音羽町3-19)よりの刊行。四六判、角背、紙装、245ページ、定価80円。装偵は伊藤廉。
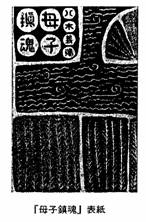

八木義徳の名は、当時の文芸雑誌で時々は見かけたが、第一次戦後派の作家に心を奪われていた時代のこととて、私の心をクイとつかむ作家のなかには入り込んでは来なかった。しかし『母子鎮魂』を読み、ついで『私のソーニャ』(昭和24年3月10日文藝春秋新社)などを入手してから、八木義徳という文学者に対する関心は徐々にかたまり、彼の著書を出来るだけ多く集めてみようと思うようになった。とくに八木が終始一貫横光利一を敬愛、その門下生としてふるまったことを知るにつれて、志賀直哉に対しての瀧井孝作・尾崎一雄・網野菊などと同じく強烈に私の視野のなかに入り込んで来た。のちには野口冨士男との縁の深さも急激に加わって来た。
『母子鎮魂』には、本の題名となった「母子鎮魂」をトップに、「帰来数日」「仏壇」「相聞歌」「胡沙の花」「劉広福」の六編が収められている。今日ならば、芥川受賞作の「劉広福」を書名にし、トップに掲げるのが常のかたちであると思う。しかし戦争末期の「日本文学者」に掲げられ、「文藝春秋」に再掲載された「劉広福」は、この時点ですぐ単行本に、というわけにはいかなかったろうし、戦後復員した八木にとっては、家は空襲で焼かれ、妻と子とはともにそのなかで死去という打撃を受け、そこからの再起は決して容易なものではなかったはずである。しかも横光利一の死去、横光に対しての数々の批判、第一次戦後派の作家たちのせきを切ったかのような動き。それを眺めながら自分なりの作家としての立ちなおりをはからねばならない苦渋。それは大岡昇平や梅崎春生よりも率直にいってむずかしい立ちなおりであった。また復員がえりの田村泰次郎のような、なんでも来いのふてぶてしさを押し通して
いく強引さは八木にはなかった。本質的にいって八木は乱世をスイスイと乗り切っていくタイプではなく、自己の内からのテーマを静かにあたため、ゆっくりとそっと質朴に提出していくタイプの文学者であった。
芥川賞受賞作は、この時期の彼にとっては二の次の問題であり、まず廃墟の中で死去した妻と子への呼びかけの作品が、人間としての八木の内からの声として必然性を持っていた。芥川賞自体、まだこの時期には復活もしていなかったのである。書名も、作品の配列も、『母子鎮魂』とせざるを得なかったことも十分納得出来る。
土合弘光の作製した「年譜」にあるように、八木は「昭和19年2月」に「劉広福」を脱稿し、「3月」に応召、「石川県金沢市東部第四九部隊に二等卒として入隊」「門司港から中国青島に上陸」「10月、湖南省長沙から衡陽への行軍途中、〈日本文学者〉創刊号に掲載された『劉広福』に芥川賞授賞の通知をうける」。時に33歳であった。翌「昭和20年」の項には「前年末より南部奥漢打通作戦に参加。8月15日、敗戦」。ついで「昭和21年」の項には「約九か月の抑留生活を経て、5月に復員。妻りよと長男史人が、前年3月10日未明の東京大空襲で弟妹三人とともに焼死したことをはじめて知る。兄夫婦の家にころがりこむ。7月、〈早稲田文学〉に「帰来数日」、12月〈文藝春秋〉に「母子鎮魂」を発表。翌22年の項には「3月、〈新潮〉に「仏壇」。10月〈文学界〉に「相聞歌」。11月、〈文芸〉に「わがつれづれ草」を発表。12月、師横光利一「胃潰瘍に腹膜炎を併発して逝去。享年49歳」と記されている。「胡沙の花」を除く他の小説が、戦前から続いていた著名な雑誌に掲載されていたことがわかってくる。
「母子鎮魂」は、「りよ子、史人よ」と妻と子供に幾たびも呼びかけつつ、復員前後の「ぼく」の心情がストレートに述べられていく。山口県の「仙崎」という港に着き(この「仙崎」は今日西條八十によって見出された童謡詩人金子みすゞとのかかわりで一躍著名になった)、復員列車に乗って上京、東京の東中野の家(これは5月)と下町の実家に留守を兼ねて帰っていた妻と子供が3月10日の東京大空襲によってすべて死去していた事実を知る。そこであらためて「戦争」とは、「家が焼け、人が死ぬ」ことではなく、「自分の家が焼け、自分の妻や子が死ぬ」、ことだと気づく。戦地にいた時には「戦争」の全体が判らず、「戦争」が終り、「地方人」になった今、やっとそれが判った。それを「何という愚かな賢さ」と自己を眺めるもうひとつの眼を挿入する。また「処置ナシ」か、という軍隊ではしばしば口にしていう言葉で笑ってみせる。痛烈な打撃を受けながらも、「処置ナシ」ですましてしまうところに八木義徳の逆のふてぶてしさがにじみ出ている。
家の中に上る前に、まづぼくはいきなり素っ裸になるだらう。ぼくが戦地から持ち帰ったものの一部 ― 背嚢も、雑嚢も、軍靴も、儒絆も、袴下も、下帯も ― それらはこの戦線三年間の生活の、汗と脂と挨りと、蚤と風と南京虫と、さうして「俘虜」の臭ひが、到るところに、抜き難く、シミついていゐる筈だ ― これらのものをまづ緒麗さっぱりと脱ぎ捨て、ひとまとめにそちらへ投げつけて置いて、さて、冷水を満々と張った盥【たらい】の中にたっぷりと漬かるだらう。頭の上から冷たいシャワー代りに浴びせてもらふだらう。
この「ぼく」の家に帰ったらどうする、という思考と行動は、捕虜生活を経て復員した私の場合とて同じであった。もっとも私はスマトラの南部パレンバンの守備隊、しかも敵機は一機も現われず、現地の人とのトラブルは一切なく、実弾は一発も撃たないで、それで食糧は確保されていて、敗戦のことを知らされたのも一週間ほど経てから、という奇妙な体験であり、一年有余してからの復員で、帰ってみれば家は廃墟、父はすでに中学時代に死去、母は空襲以前の段階で死去、妹らは離散、焼けあとに慌然と佇んだという経験を持っている。その焼けあとの土地を二束三文の価でたたき売り、上京、オクテの進学の方向につき進んだ私。八木義徳はここで中国大陸における軍隊の内部、その全体像を全視野に入れて、作品を提出しようとしたのではなく、「りよ子、史人」への鎮魂、とくに「史人」を全面に出し、聞き出した彼らの姿、かつての生活をふりかえりつつ、本人は立ちなおりの契機をつかもうとする。よき音楽への愛着を持ったが故に、「あの陳腐生硬な詞句と、あの卑俗低劣な曲調による軍歌のために、いかに日本の兵隊の心は殺伐にさせられたか。その殺伐な心のために、いかに日本の兵隊は野獣の如きものにならねばならなかったか」というような批判的な言葉も飛び出してくる。しかし残念ながらこの「母子鎮魂」は、細部への具体的な描写があまりにも少なすぎる。とくに「史人」の死は肉体の内部にまでこたえ、「父は三十六歳、すでに見切りのついた人間であった。父はその人生の半分は投げ、半分は執着してゐる中途半端な人間であった。しかしその人生はすでに薄明の霧の中に暈【ぼか】されてゐる人間であった」と自己を責める。「風船玉は、パンと音を立てゝ破れたのだ…」という空虚感。「りよ子」と「史人」との立体的な人間像は抽象化され、「ぼく」の心情が全面に出ている。いやこの「ぼく」のやけくそ寸前のうちのめされかたもまだ十分に描ききれたとは言い難い。
それよりも「帰来数日」のなかの、
実に恥かしいことだが、私は妻や子に会ひたいのであった。死んだ妻や子の顔が見たいのであった。子供を膝に抱き、妻に愛の言葉をかけてやりたいのであった。
あの運命的な八月十五日 ― 私は地べたへ叩きつけられ、へたばつたと思った。自分の人生もこれで終りだと思った。希望も理想も夢も、一切霧散したと思った。私は自棄【やけ】になりたかった。しかし自棄になることは出来なかった。私はこれまでの人生の中、三度大きな自棄をおこした。四度それを繰り返す気にはなれなかった。地べたへ叩きつけられた私は、もがきながら、手がかりを、足場をもとめた。この暗闇の模索の中で、私の手に触れるものはそれもこれもこんな暖昧で多少インチキ臭かった。でなければ、あやふやで、たよりなかった。私は素朴で確かなものを欲した。そしてその結果、私は極めて平凡なものを掴へたのである。
こういう覚悟のもとに八木義徳の戦後は徐ろにスタートを切る。といってもまだ種々の曲折を経るのだが、『私のソーニャ』を経て、山梨県出身の中込正子と出あい、ストレートな告白をすることで再婚。質朴でキチンとした正子との結婚生活のなかで、八木義徳は作家としてのゆるぎない自信を得ることになる。実は八木の父も、またもともとは山梨県出身者であり、室蘭で妾の子として出生したのだが、そこで身につけた野性の本能、八木のいう動物的精気は、正子との生活のなかで、徐々に発揮。その間耐え抜く日々は続くのだが、『母子鎮魂』や『私のソーニャ』を土台にすることによって、彼の忍耐力は驚くばかりの持続していったのである。
「仏壇」という小説のなかには、
彼自身は終日兄の家の茶の間の長火鉢の前に、ごろりと芋虫のやうに躰を横たへたきり、ぴくりとも動かぬのであります。
というような「動」に転じらぬ鬱の日々があったことも事実である。しかしそういう彼に対して兄も嫂も一度も不愉快な顔をせず、やがて中込正子との縁をとり持とうとすらしてくれたのである。他の縁談の話もあったようだが、つまるところ中込正子と決めていくプロセスについては、まだこの時点では書かれていないが、この時点の八木にとって中込正子の存在は、彼女の意識の内容よりも強烈であったことは確かであった。
そういうなかでの横光利一の死去は、八木に切実以上のものがあったに違いない。それは妻と子を喪ったことと同質といってもよい。「母子鎮魂」と横光利一の死去。それは八木を襲った嵐、いやハリケーンともいうべき暴風雨であったが、それをわが肉体で受けとめつつ、中込正子との再婚につき進んだとき、八木の文学の血路は切り開かれていったと私は受けとめている。
横光への思いについて八木は種々書きためている。『風祭』により読売文学賞を受賞した直後の第一エッセイ集『男の居場所』(昭和53年10月17日北海道新聞社)は、彼の小説とあわせて読むべき重要なエッセイ集である。といってもその「あとがき」にあるように、「これらの文章のなかには、碁や将棋や麻雀などの話は一つもない。釣りやゴルフや山登りなどの話もない。犬や猫や小鳥や花や樹の話もない。芝居や寄席や、性や食べものについての話も一つもない」「われながら呆れるほどの無趣味、無道楽、無風流である」「文字通りの野暮天というのが、私の知った私白身の地顔だが、いまさらこんなことを知っても、もう手遅れである。この野暮天の地顔をそのままさらけ出すよりほかはない」と述べられているが、その「野暮天」そのものが、八木義徳の人間としての、文学者としての質朴さ、誠実さに、そのまま直結するものなのである。
ここには横光について四編のエッセイが収められている。その第一の「師・横光利一に……」(「新潮」昭和32年4月)は、横光の没後十一年になって書かれたものである。「横光利一先生」と八木は文節を改めるごとに数度も呼びかけ、「あなたが亡くなられてから、もう十一年になります。毎年大つごもりを翌日にひかえた十二月三十日の夕方、あの世田谷池ノ上のお宅にうかがって、あなたのお写真と御位牌の飾られた仏壇にお線香をおあげするのも、かぞえてすでに十一回になります。そしてこの行事を終えてはじめて、「あゝ、ことしもあと一日で終りか」とわが師につぶやいて、年の瀬の感慨をあらたにするというのが、またここ十年来かわらぬ私の習わしでもあります」と書く。このように横光の没後、毎年末の忌日に、参上する作家が果たして幾人いたであろうか。『旅愁』のころより、いや戦時下を含め、戦後の横光批判のきびしさは、かつての昭和文学の開拓者の光栄をかき消すほどの力を持っていたのに、わが作風とまったく異なる八木義徳が、このように横光への思慕の情を持ちつづけ、実行に移していたとは……。また末尾のほうで、再び「横光利一先生」と呼びかけ、
私の学生時代からあなたの死の直前まで、十三年間、私のあなたから学んだものは果して「小説作法」であったでしょうか。一度として私はあなたから文学に関する「指導」をうけた覚えはありませぬ。同人雑誌に書いた私の幾つかの小説は、そのつどたった一言、
「ダメ!」
でありました。文字通りたった一言、しかも爽快きわまる「ダメ」でありました。そして私もまたあなたのその一言で十分であったのであります。なぜといって、あなたの例の特徴ある大きな声(ある瞬間、あなたのお声は突然一オクターヴも高くぴょんと飛び上がるのでした)で、「ダメ!」といわれると、とたんに私はある精神的な快感を感じたからです。しかし、あなたの「ダメ」はやがて「幽霊」という言葉にかわりました。
「きみ小説はうまくなった。しかし、まだ幽霊が出ないぞ」
あなたのおっしゃる「幽霊」とは悪魔のことでありました。そのころ私はすでにジイドの「すべて創造に関係は、悪魔の助力なしには到底成就し得ない」という言葉を知っていたからです。けれどもどうしたら自分の作品にその「幽霊」が出るのか ― 例によって
あなたは一言も明しては下さらなかった。しかしまた私にはそれだけで十分でありました。なぜといって、すぐれた小説には必ず「幽霊」がいることをあなたやジイドにイヤというほど叩きこまれたからです。
いまにして、あなたが亡くなられてから十年経ったいまにして、私はハッキリとあなたにお答えすることができます。「幽霊」とは、作家がそこに賭けたものの代償である、と。そうです。あなたは賭けたのでした。あなたの全才能を。いや、あなたの全人間を。
そして私のあなたから学んだものも「小説作法」ではなく、あなたの「人間」でありました。一人の人間はいかにして芸術家となるか、同時に、芸術家はいかにこの世に存在し、いかにこの世に生きるか ― 私にとって、あなたはこの命題の典型的な体現者であります。
石原慎太郎の「太陽の季節」の登場により芥川賞は一躍文壇の片隅から祉会的現象として脚光を浴びていたころ、かつて「劉広福」によって芥川賞受賞者となった八木義徳の存在は心ある一握りの文学者、編集者によってのみ尊重されていたが、まだ評論や研究の真正面からの対象とはなっていなかったのである。『母子鎮魂』においても、「劉広福」のみは、末尾に小さくちぢこまっていたし、本のなかでは浮いた位置に置かれていたのだ。
「色褪せし守袋」は、船山馨のところにあった横光の書の掛軸 ― 「コンコルド/女神ふけにし/春の雨/横光」 ― を船山宅を訪れてそれを眺め、その日は「イヤシイロは利かず」帰り、再び船山の家を訪れた時、素直に、 いきなり、「おい、船山、あれをオレにくれ」と言うと、船山は「おう!」と叫び、「林芙美子さんからもらったものだが、オレが持っているより、きみが持っているほうがいい」ときっぱりと手渡したという話だ。「コンコルド」の句は『旅愁』のなかに出てもくる。林芙美子が銀座の「はせ川」で、ねだって書いてもらったものである。横光は筆がなく、割箸の先を歯で噛み、それを筆代りにして書いたものだ。芙美子の母の古い帯地を使って表装したという珍品である。こういう八木のストレートな実直さを、船山も十分承知の上で手渡したこの挿話も、私はきわめて好ましい人間と人間の関係と思っている。
〔こうの・としろう早稲田大学名誉教授〕
― 国文学解釈と鑑賞 平成18年1月号より転載